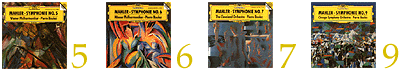ブーレーズによるマーラーのシリーズは、ここのところ前半の作品が多くなって来ているようだが、交響曲第四番はクリーブランド管弦楽団との共演である。
|
冒頭まず、その軽快なテンポとリズムに、あまりの心地のよさで、私はびっくりしてしまった。いつもと同じくすっきりとしていて、音楽の性質もあって、とりわけさわやかな響きは、聞いている我々を新鮮な気持ちにしてくれる。テンポの速いところでは、快調の足どりで進み、リズム感や響きのコントロールは明瞭であっても、ここではかなりの流麗な印象を受ける。しかし一方で、全体を通して、音楽をひとつひとつ丁寧に構築していくブーレーズの姿勢は相変わらずであり、ここでもそれはやはり冴えわたって、鮮やかでもあり、だいぶ丸みを帯びた音楽に変わってきてはいるけれど、核心の部分では非常に引き締まったものをもっている。乱暴に聞こえてくることは全くなく、落ちつきが安心感を与えてくれるのは、私には特に魅力的にも感じられた。
|
クリーブランド管弦楽団の音がまた特に素晴らしい。なんと透明な響きで、美しいことであろう。ブーレーズの耳はすさまじく、その絶妙なコントロールは神業だと思う。普段からクリーブランドはたいへんに素晴らしいと感じられており、ドホナーニが指揮しているときも私には特に魅力的なオーケストラなのだが、なぜこうも指揮者の存在で演奏は大きく変わってしまうのであろうか。それぞれの楽器の名人芸もあると思うのだが、室内楽的な効果の強いこの作品で、そうした傾向はよりいっそう高められているように思われる。もちろんブーレーズによる音楽的解釈もそこには大きく影響しており、オーケストラが指揮者の細かな指示によく応え、そうした成果の表れであるともいえるであろう。ブーレーズとクリーブランド管弦楽団の関係、その相性は特に良好であり、ここでもそれを強く実感したのである。
|
終楽章では、最近話題のユリアーネ・バンゼが登場している。ここではそれも聞きどころであるといえると思う。ブーレーズは比較的速いテンポで、あっさりと進めるが、バンゼの歌は落ちついており、雄弁にも感じられるその語り口は素晴らしかった。マーラーの音楽に特に適した歌手であるということもいわれているが、おそらくこれから、世界の大舞台で登場する機会も多くなるであろう。注目の歌手である。
|
この交響曲は、マーラーの作品でも、特に優雅で、繊細な表情による美しい響きをさせる音楽であると感じられるが、ここでのブーレーズの演奏は特に傑出していると思う。音楽そのものが天国であるともいえるのだが、聞いていて、これほどに幸せな気持ちにしてくれることもそうはない。たいへんに素晴らしい演奏に出会え、それを創造してくれたブーレーズに対し、私は感謝の気持ちでいっぱいである。
|


 DG 463 257-2
DG 463 257-2